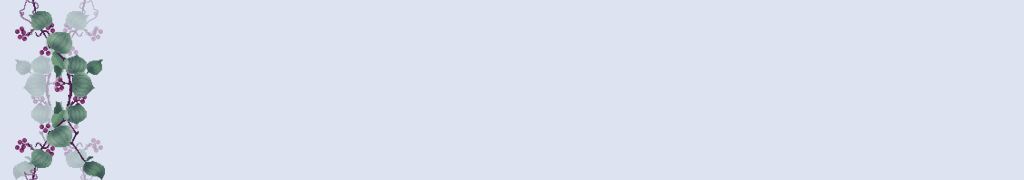
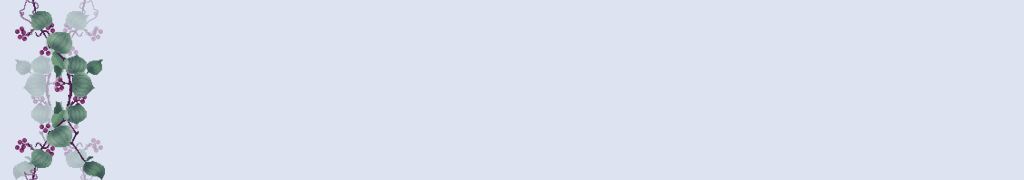
現代能楽集III 『鵺/NUE』
2006年11月14日(火)19:00~ 於:シアタートラム
監修:野村萬斎
作・演出:宮沢章夫
※劇中劇 清水邦夫 作
「朝に死す」
「想い出の日本一萬年」
「真情あふるる軽薄さ」
「ぼくらが非情の大河をくだる時--新宿薔薇戦争」
演出家:上杉祥三 黒ずくめの男:若松武史 桐山雅子:中川安奈 俳優:下総源太朗
若い俳優:半田健人 映像作家:上村聡 マネージャー:鈴木将一朗 女優:田中夢
※舞台本編の感想はブログにて。
◆ポストトーク
世田谷パブリックシアター芸術監督:野村萬斎
『鵺/NUE』演出:宮沢章夫
世田谷パブリックシアター・プログラムディレクター:松井憲太郎
終演後、10分ほど休憩をとって午後9時15分からトーク開始。舞台上は『鵺』のセットがほぼそ
のままで、椅子が3つ足されて向かって左から司会役の松井さん・演出の宮沢さん・芸術監督ド
ノが着席。宮沢さんは濃いめのモスグリーンのロングスリーブシャツにブルージーンズ(ほぼ普
段着・笑)、芸術監督ドノはベージュのジャケットにグレーのボトムでマスクは当然外して(笑)。
トークの内容は「ユリイカ」11月臨時増刊号の対談とほぼ同じ様な内容で進んでいったと思いま
す。演出の宮沢さんがトツトツと喋る方で、つられて(?)芸術監督ドノもトツトツと(笑)。聴き取
りづらいところが多かったことと、帰りの時間がだんだん心配になってきて(泣笑)ラストの方は
正直、心此処にあらず状態だったことで、メモが上手く取れていませんので、断片的なご報告に
なってしまっています申し訳ございません。補足・訂正は他にご覧になった方と「ユリイカ」にお願
い致します(汗)。
現代能楽集も3回目。今回選ばれたのは『鵺』。現代的ドラマ化しづらいと思っていたが「【芸術
監督ドノ・以下"萬"】稽古の時から拝見して、今日も観て、意外に楽しくなっていた。思ったより
笑いもあった。(宮沢さんに)少し中身変えましたか?」「【宮沢さん・以下"宮"】シナリオには無
い"名刺交換"のシーンは稽古中に決まりました(笑)。」「【萬】舞台をなごますためですか?計
算通りとか(笑)?」「【宮】…自分が笑いたかったんですよね(場内大笑)。稽古の中でどんどん
変化していくのが楽しい。」
「【萬】能『鵺』の複式夢幻能の手法を取り入れてますが、過去に抹殺された人々にスポットを当
てる原作の主題が、今回の劇の主題とマッチしていた。」「【宮】今という時代の中で過去のモノ
をどう呼び覚ますか?現代能楽集のお話をいただいて、能という形式と、今回設定した"空港の
トランジットルーム"という空間が、たまたま一致して話が進んでいってくれた。」
「【萬】シェイクスピアとかチェーホフとか、現代にしっかりと残っている昔の戯曲はたくさんあるん
ですが、現代作家の戯曲はすぐ消えてしまう傾向にあるんですが。」「【宮】数年ですぐに絶版に
なってしまうんですよね。ホント売れないんです(宮沢さんの苦笑いに場内大笑い)。」
「【萬】この劇中劇は、自分が生まれた'60年代後半の頃の小劇場や新宿の様子を見せていま
すが、当然自分はリアルタイムでは知らないので、全部ではありませんが清水さんの戯曲を後
追いで読んだり、当時を物語る映像や文章で知識として知りました。」「【宮】清水さんの戯曲は
以前から良く読んでました。最近蜷川さんがちょくちょく清水さんの戯曲を取り上げていて…あ、
この前の舞台を観に来てくれたんですよ蜷川さん。"アレ(演出家)は俺だ"って(場内爆笑)。」
「【宮】清水さんの戯曲の中に出て来る"船"のイメージと、能『鵺』の"舟"のイメージが一致した
んです。能と清水作品が偶然にマッチした。そこに現代能楽集の企画があって、とにかく今回は
本当にいろいろな偶然が重なったんですね。」
「【宮】清水さんの戯曲はある人達("ある世代の人達"という意味か?)にとってはとてもロマン
ティックでナルシスティックなモノなんですが、僕は別の側面からこれらの戯曲に光を当てたいと
思い、その為にこの現代能楽集があったわけです。」「【萬】清水さんの戯曲をかなりいっぱい使
っていますが…」「【宮】そこのところは著作権の問題もあって気に掛けてましたが、清水さん御
本人から快諾を受けることが出来て良かったです。」「【宮】自分のオリジナルと言ったって、どこ
までが完全なオリジナルか分からないし、無意識に過去のモノを引用していることもあります。言
葉が深い歴史の地層を掘り返すように。」
「【萬】(稽古での)演技のルール作りみたいなものは?」「【宮】セリフの意味よりは、音として観
客にどう伝わるかを考えました。音楽のように語って欲しい。稽古を進める中で、だんだん意思
統一されていったと思います。稽古中はいつも大騒ぎだったんですよ。だから自分がいつも"落
ち着け!"って言ってたんです(笑)。」
「【萬】こうやって舞台を見ると、椅子が置いてあるくらいでいたってシンプルな空間ですね。能舞
台と同じです。こういうところで演じるには、声や身体の高いレベルや集中力が必要になります
ね。」「【宮】演出はどんどん引き算して削ぎ落としていきました。」「【萬】清水作品の"当時の"発
声法でやると、それはタダの"時代作品"になってしまう危険がありますね。」「【宮】正確に伝え
れば、その言葉の持つ力もちゃんと伝わると思います。」
「【司会】(宮沢さんに)演出家として"役者・野村萬斎"を引きずり込むとしたらいかがでしょう?」
「【宮】それはもう…萬斎さんはとにかく声が良い、凄いですからね。狂言というのも凄い。以前、
京都造形大学で同じ演目を歌舞伎と狂言で演るというのを見たんですが、歌舞伎が合理的結
末に持って行くのに対して、狂言は不条理な結末でオチをつけて笑わせてしまう。こういう笑い
は日本の笑いの中でも特殊だと思います。」「【萬】自分が演出をする時も、まず音声的なところ
に重きを置きますね。最近の演劇では、舞台にキャラ立ちしてるのが勝ちという価値観ですが、
自分の場合はそういうキャラクター勝負ではなく、舞台に乗っている者同士の声のアンサンブル
とかに留意してます。」
「【宮】前にシェイクスピアを演出した時、最初は役者さん達に"好きにやって"と指示して始めて
その後少しずつ調整していきました。稽古場で稽古しながら"その人の魅力"はどこにあるのか
探して引きだしていくんです。」