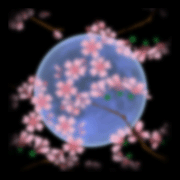
2002年10月12(土)・13日(日) 於 : 茨城県 下館市民会館
【10月12日(土)】 能「百萬」 シテ:観世榮夫 ワキ:鏑木峯夫 アイ:野村萬斎 他略
狂言「昆布売」 大名:野村萬斎 昆布売:深田博治
能「猩々乱」 シテ:観世榮夫 ワキ:鏑木峯夫
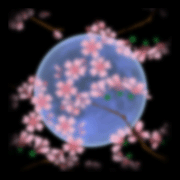
能「百萬」
ある僧が、拾った少年を連れて京の嵯峨に赴く。寺の門前で僧が念仏を
唱えていると、女が現れた。この女はひとり子を失い笹を手に狂い歩い
ている。子の行方を尋ねて諸国を巡った身の上話の曲舞を舞う。そのう
ち、僧に連れられているのが我が子と知り、女は正気に戻る。
大まかなあらすじはこんなところです。母子物とあってストーリーに展開があり、難しい中にも理解出来る
部分がありました(汗)。間に萬斎さんが出ました!当日まで知らなかったので、嬉しかったです。萬斎さ
んが橋掛かりで控えている時から、目がそっちに行っちゃって(苦笑)。この日の肩衣はyoiya10月号「万
作夜話」の写真で、月崎さんが着用している物でした。物狂いの女を紹介する役だったんですが、そこだ
け軽妙で、「南無釈迦〜南無釈迦〜♪」と謡い、舞って切戸に消えて行きました・・・。やっぱりモミアゲは
細く整え長めでした(もう定着していますね)。
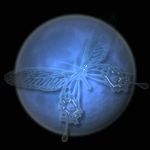
狂言「昆布売」
大名萬斎さんは、青地に白い扇面を散らした衣装。中の着物は、白地に紫でし
た。私の座席は舞台向かって右手の2列目で、センターとの通路側でした。萬
斎さんは脇柱寄りの立ち位置で、舞台前方ギリギリまで出る事が多く、近くて観
やすく満足しました。
さて「昆布売」ですが、大名が昆布売に太刀の持ち方を指南する場面や、立場が逆転して昆布売に脅さ
れて、不承不承昆布売を引き受ける場面、場内爆笑です。「やるわいやい、やるわいやい」情けない顔
で引き受けた割りに、教わった売り声は次第に本職をしのぎ、「平家節」「小歌節」「浄瑠璃節」と深田さ
んに続いて謡うんですが、その声の良い事!最後の「踊り節」では、茶目っ気たっぷりなノリノリの表情
で舞い踊り、本職深田さんをして「器用なヤツじゃ・・・。」と感心しらしめ、大受けでした。今でも謡いの
「昆布召せ 昆布召せ 御昆布召せ♪ 若狭の小浜の召しの昆布♪」が私の頭の中をクルクル回って
います。
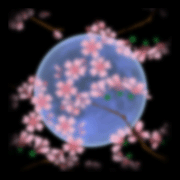
能「猩々乱」
唐土の揚子の里に、高風という孝行な酒売りがいた。そこに海に住む
猩々が来て、酒を飲んで舞い戯れ、汲んでも尽きない酒瓶を高風に与
えて祝福する。
猩々は、皆さんもどこかで見たことあるかと思います。その扮装は赤頭をかぶり、笑みをたたえた赤い
童顔の専用面(猩々)を着け、上着も袴も金襴の赤という赤ずくめの物。酔いと無邪気な童心の象徴な
んだそうです。能というより舞いに近いのか、変化の多い動きと時間の短さに集中して観ることができ
ました。
今回は「薪能」という名ですが、屋内での公演でした。来年は屋外だそうです。その場合全席自由なん
で、場所取りが大変そう・・・。能は2度目ですが、演目に変化があって楽しめました。あまりに緩慢な時
は、遠い昔に思いを馳せます。その昔、大名や奥方などが楽しんだその時の時間の流れは優雅なもの
だったんでしょうね。
【10月13日(日)】 能「野宮」 シテ:梅若吉之丞 ワキ:高橋正光 アイ:野村万之介 他略
狂言「腰折り」 祖父:野村万作 山伏:竹山悠樹 太郎冠者:月崎晴夫
半能「山姥」 アイ:梅若吉之丞 ワキ:鏑木峯夫
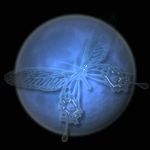
能「野宮」
旅の僧が京都嵯峨野の野宮の旧跡を訪ねると、若い女が来かかり、この野宮
は昔、六条御息所が伊勢の斎宮となった息女と共に籠った所だと話し聞かせ
る。御息女は皇太子妃ろしてときめいた女性だったが、夫に死別し、その後に
愛を得た光源氏からも見捨てられて、昔に変わる寂しい身の上となり、涙なが
らに伊勢に赴いたのだという。そう物語った女は、実は自分がその御息所なの
だと名乗って消え失せる。夜になると、御息所の霊が昔の姿で現れ、賀茂の
祭り見物のおりに、車を据える場所を光源氏の正妻の葵上と争って恥辱を受け
た思い出などを物語り、懐旧の思いにひたりながら舞を舞う。
「源氏物語」賢木の巻からの名品。シテの梅若吉之丞さんは重要無形文化財(つまり人間国宝)保持
者です。舞台中央に簡素な黒木で野宮の鳥居を作り、枯れた趣を演出していました。しかし、長い!
1時間20分強の大曲でした。アイの万之介さん、いい味出してました。能のシテは面を着けているた
め声がくぐもりがちなんですが、万之介さんの明瞭な発声に、緩慢な場面にメリハリが出来、グッと引
き締まりました。さすがです。
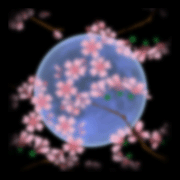
狂言「腰折り」
羽黒山の山伏が大峰、葛城で修行して故郷の祖父を訪ねる。祖父は孫
をまだまだ子供だと思っているようだ。山伏は祖父の腰が曲がっている
ので、孝行心から行力で直そうと祈り始める。しかし行力が強すぎて祖
父はあおむき、それを直そうと再び祈ると今度は前に曲がり倒れる。祖
父はとうとう「年寄りをなぶりに来たな」と怒り出し山伏を追い込む。
万作さんの祖父、出からすでに笑いを誘っていました。細い体をくの字に折り曲げて、ようよう歩く爺そ
のものでした。思わず客席から「うまいなぁ〜」と感嘆の声がもれたほどです。竹山山伏、やはり膝を
上げてヒョイヒョイと不思議な山伏ウォーク。大真面目な顔がハナからうさんくさいです(笑)。月崎太郎
冠者はなんと前日のアイで萬斎さんが着た肩衣を着用していました(お手入れが大変なんで着回し?)
葛桶に腰掛けた万作爺に行力をかける度に、爺は「ひえッ」と悲鳴をあげながら何度も飛び上がり、ま
るでバネ仕掛けのお人形のようです。悲鳴も可愛くて大受けでした。最初はうまく術がかかり「爺様孝
行のいい山伏」だったのに、祈れば祈るほど今度は「年寄りをオモチャにしている悪いヤツ」になってし
まって、最後はいつもの追い込みで終了。面白かっただけに、20分がほんとあっという間に過ぎてしま
いました。
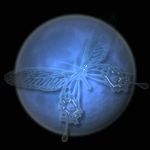
半能「山姥」
夜がふけるとまことの姿の山姥が現れ、遊女の謡う曲舞に合わせて舞った末、
本当の山めぐりのさまを見せ、峰を伝い、谷を駆けて姿を消す。普通には恐ろし
い鬼女とされる山姥も、実は人を助ける山の女であるとし、邪正一如、善悪不二
の理を象徴する存在として描かれたというもの。
白頭に鬼女の面、迫力のある舞いでした。正味50分くらいでしたが飽きませんでした。終盤は橋掛か
りも使ってスケールの大きな世界を出現させてくれました。さすが人間国宝(ブランドに弱い)良い物を
観せて頂きました。