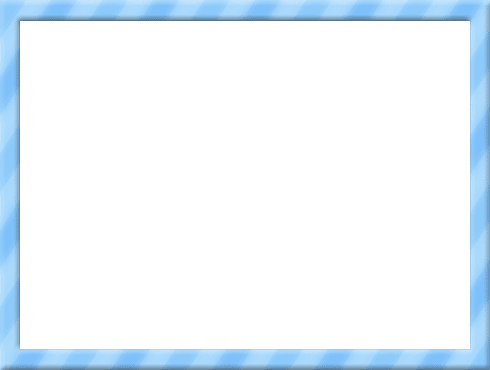
2003年5月10日(土) 16:00~
於:横浜能楽堂
【番組】
Ⅰ 狂言解説 石田幸雄
Ⅱ 狂言『文蔵』
主:野村万作 太郎冠者:野村万之介
後見:高野和憲
Ⅲ 狂言芸話(四) 野村万作
Ⅳ 狂言『弓矢太郎』
太郎:野村萬斎 当屋:石田幸雄
太郎冠者:竹山悠樹
立衆:深田博治・高野和憲
月崎晴夫・破石晋照
後見:野村良乍
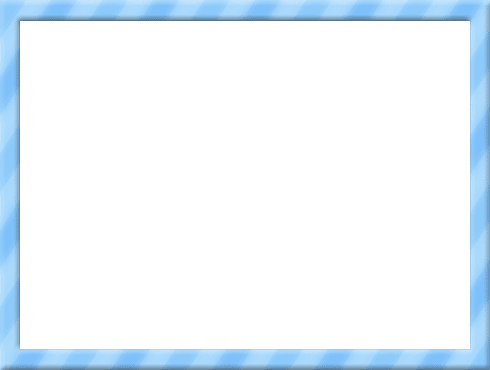


横浜能楽堂への
道しるべ。桜木町
駅から何回か見
かけました。この
道しるべは能楽
堂直前のもので
すが、ここに至る
までの道のりが
険しかった(苦笑)。結構急勾配の
「紅葉坂」を登って行きます・・・。大
して長い距離では無いのですが、日
頃の運動不足を露呈してしまいまし
た(爆)。へろへろ。
横浜能楽堂正面。道
を挟んで反対側に県
立図書館があります。
13時の部をご覧にな
った方々とここで落ち
合って、16時の部の
開場が始まるまで、し
ばし立ち話(笑)。
「2階席って観やすいですよ~♪」と慰められて(苦笑)行って参りました横浜能楽堂。自宅最寄り
の駅から電車一本、乗り換え無しで行ける好条件の桜木町でしたが・・・さすがに乗り疲れた・・・。
13時の部をご覧になった方達も含めると、かなりの人数にお会い出来ましたね。萩大名様・アン
様・鳥木子様・さつき様・波華様・和音様・薫風様&蚊ちゃん・ピカ様・クノイチ様・・・とりあえずご
挨拶出来た方々だけでもこれだけいらっしゃったので、きっと他にもぞくぞくと(笑)??
5月の風が爽やかな、ハマの丘の上でした。しかし・・・「紅葉坂」・・・老体にキツイよ(爆)。
最近、HNを伏せ字にしません(爆笑)。マズかったら言って下さい(ヲイ)。
Ⅰ 狂言解説 石田幸雄

(2階席より)
黒紋付姿で石田さん登場!ここのところ、石田さんのトークを聴く機会
に恵まれております(笑)。いつもの様に飄々とした雰囲気♪
通常のトークですと、「狂言とは何か?」といったような初心者向けレク
チャーになるところなんですが、今回は万作師がシテを演じる『文蔵』
を観るにあたっていささか基礎知識が必要、との事でこの『文蔵』につ
いての解説となりました。
『文蔵』の中に「源平盛衰記」の"石橋山の合戦"の長いくだりが語られ
ます。幽閉されていた源頼朝が1180年に平家に対して、伊豆で挙兵し
た際の様子を語っているそうですが、ここでの頼朝の軍勢は300、対
する平家の軍勢は3000、というもの。この劣勢をひっくり返す為に、頼朝は夜軍の将として真田与
市義貞を立てます。それに対して平家方は橋野五郎景久を立て、両者の一騎打ちとなります。
『文蔵』ではシテである主が、この"石橋山の合戦"のくだりを延々と語るのですが、葛桶に座って
語るだけでなく、謡いや舞の要素も入ってくる。特に「語り」の部分は普通の狂言よりも非常に様
式性が高い、という事でした。
この語りはいわゆる「候(そうろう)文」なので強い文語調であり、真田氏のいでたちやその戦いぶ
りを緊張感溢れる口調で語っていくのですが、その中にポロッとギャグが入っている(笑)、そこの
ところを是非楽しんで欲しいそうです。
また、演劇的に「?」と思ってしまうシーンもあるそうで(石田さん、「そこはサラッと通って下さい」と
仰ってました・笑)。最初は主が太郎冠者の私宅に赴いて話をしているのですが、いつの間にか
舞台が主の家にワープ(??)しているらしい(爆)。「あまり深く突っ込まないで観て下さい」と石田
さん(大笑)。
Ⅱ 狂言『文蔵(ぶんぞう)』 主:野村万作 太郎冠者:野村万之介
主に無断で旅をしてきた太郎冠者が、これまたその報告もせずに帰宅。それに腹を
立てた主が太郎冠者の私宅押しかけて折檻しようとするが、太郎冠者が「京見物を
してきた」と言うと、京を懐かしむ気持ちが湧いてきて、今回は太郎冠者を許す事に
する。話によると、太郎冠者は東福寺に住んでいる主の伯父を訪ねて、そこで珍しい
ものをご馳走になったと話す。それは何か、と主が尋ねるが、物覚えの悪い太郎冠
者はどうしてもその食べ物の名を思い出せない。そこで太郎冠者、主の愛読書であ
る『源平盛衰記』の"石橋山の合戦"の中に出て来る食べ物をいただいた、と言う。
太郎冠者が何を食べたかどうしても知りたい主、思い出させようと床机に腰を下ろし
てその場面を語り出す。やがて語りの中で、真田与市の乳母親(めのとおや)の文
蔵なる名前が出た時、太郎冠者は「それ、その"文蔵"を食べた」と言い出す始末。
それがどうも"文蔵"ではなく"温糟粥(うんぞうがゆ)"の事を言っているのだ、と分か
る。太郎冠者は「ぶんぞう」と「うんぞう」を混同していたらしい。
万作師・万之介師の両ヴェテランによる演目。今京から帰って来たばかりだと言うのに、ご馳走に
なったモノの名前を忘れてしまった太郎冠者、「・・・忘れてしまいました・・・」という万之介師のとぼ
けた雰囲気に思わずクスリ。万之介師、立ち上がる時にちょっとおみ足が辛そうなのですが・・・。
京の話をすることで許された太郎冠者ですが、どうしてもご馳走になったものの名前が思い出せ
ない。「温鈍(うんどん)」でもない、「ぬる麥(うどん)」でもない、「あつ麥(熱くして食べるうどん)」
でもない・・・ならば「羹(かん:間食に食べる餅菓子)」か?と言われても、「きよかん(魚を材料に
した羹)」でもない、「うんぜんかん」「もんぜんかん」でもない・・・あきれた主「ならば大寒・小寒か
?」と「かん」に引っかけて駄洒落を言う始末。「それも違います」と答えた太郎冠者、主に「それは
暦の事だろう!」と逆に突っ込まれる(笑)。何とか名前を思い出してもらいたくてせっつく万作主と
のらりくらりと思い出せない万之介太郎冠者のすっとぼけたやりとりが絶妙です♪
そこで何を思い出したのか太郎冠者、「自分は"石橋山の合戦"に出て来る食べ物を食べたような
気がする」と言い出します。戦記モノに出て来る食べ物??ならばと主、床机に座って、何度も何
度も読んだので憶えてしまった『源平盛衰記・石橋山の合戦』の戦語りを始めるのですが・・・。
ここからは万作師の独壇場!!扇を手に朗々と語り出します。それまでの主と太郎冠者のとぼけ
たやり取りがガラッと変わって、ピーンとした緊張感。前半は真田与市義貞の、戦に赴くいでたち
を語っていきます。(ここからは語句解説に載っていましたが)「楊梅桃李(ようばいとうり)」「白檀
磨き(びゃくだんみがき)」「緋縅しの大鎧(ひおどしのおおよろい)」「鮫鞘巻(さめさやまき)」といっ
た聞き慣れない(大苦笑)言葉がどんどん出て来るのですが、勇壮な武将の姿が自然と浮かび上
がって来るよう。後のトークではさすがにお声が枯れていましたが、ここではビンビンと2階席にま
で声が響いてきます。お歳を感じさせない(失礼!)凄い迫力・・・。
ところが!その大熱演を、横で聴いている万之介太郎冠者が、なんともボンヤリした雰囲気で聴
いているんですねぇ(爆笑)。分かってるのかなぁ、この人・・・。主の語りに熱が籠もれば籠もるほ
ど、横でボーッと聴いている太郎冠者が可笑しくて。
「・・・で、ここまでで名前は出て来たかな?」と、突然表情を崩して太郎冠者に問いかける主。その
あまりの変わり振りに大笑い。だって急にフニャっとなるもんだから(笑)。「いや、まだです!」と、
のんびり答える太郎冠者(笑)。ここまで熱演しておきながらまだ出ないのか(爆)?
どうしても名が知りたい主、更に戦語りを続けます。いよいよ語りもクライマックス、真田与市と橋
野五郎の一騎打ち!主の語りはますます熱を帯びてきます。万作師の表情も険しくなって、緊張
感も倍増!扇さばきが華麗でした。う~~ん、ここだけ観たらまさかオチがあるなんて思えない。
しかし・・・合戦の凄まじいシーンを必死に語る主の前で・・・またもや太郎冠者はボーッと聴いてる
(苦笑)。このまま思い出せずじまいになるんじゃなかろうか、という雰囲気だったのですが・・・。
「真田の乳母親に文蔵という者がいて・・・」と主が語るくだりで「それそれ!その『文蔵』を食べまし
た!」と突然思い出す太郎冠者。文蔵、もちろん人名ですが(笑)。
「『文蔵』?・・・そりゃ『温糟粥』の事だろうが???」とあきれる主に「は~、そうでしたか~」と、こ
れまたすっとぼけの太郎冠者(笑)。「ぶんぞう」と「うんぞう」の取り違え、合戦の語りとはあまりに
も対照的なユルいオチ(爆)。終始、ヴェテラン二人の織りなす緊張とユルユルの緩和(笑)に引っ
張られて楽しませていただきました。
若い方が演じるのを観たわけではないのですが、なんとなくこの演目はヴェテランの方が演じた方
が似合うのかな~、と思いました♪
Ⅲ 狂言芸話(四) 野村万作
私にとっては初めての万作師トークとなりました。今回、これを非常に楽しみにしておりました♪
黒紋付姿で登場の万作師、さすがに『文蔵』の直後でしたので、少々お疲れかな?という面持ち
でした。しかし!口を開かれたとたん、明るくパキパキとした口調で話し始められたので、ちょっと
ビックリ(笑)。こっちの勝手な思いこみなのですが、なんとなく、とつとつと話される方なのではな
いかな~、と予想してましたので。
本日のトークは「海外公演」について。万作師が初めて海外公演をされたのは、45年ほど前に「パ
リ国際演劇祭」に参加した時だそうです。お父様の万蔵師と共に、サラ・ベルナール座にて『梟山
伏』『蚊相撲』『伯母ヶ酒』を披露。音楽家やファッション・デザイナーの方(ここで万作師、そのデザ
イナーの名前を失念してしまい、見所大笑い♪)も参加していました。
能舞台の松の絵の板をバラして運んだのですが、根っこの一部の絵の板を紛失!その場で絵を
描いてもらって間に合わせた、というハプニングもあったとか。著名な画家の方に描いていただい
たので、もしその板が残っていたらもう値段がつけられないぐらい貴重かも、と万作師(笑)。
当時万作師は『梟山伏』で舞台に立たれたそうですが、山伏が「ホーホー」と鳴き真似をすると、そ
れを観ているお客さんも「ホーホー」と鳴く(笑)。後で訊いてみたら、ふざけて目隠しをする時や、
男性が女性を呼ぶ時に「ホーホー」と言う習慣があって、パリの観客にはこの「ホーホー」に親近
感があったらしい、という事でした。海外に行くと、狂言の事を詳しく知らなくても、向こうのお客は
結構ストレートに反応してくれるのが良いそうです。
1963年には米国シアトルのワシントン大学で教鞭を執った万作師。「シアトルは魚が美味しくて日
本人がいっぱいいて、良い所でした」との話にまた見所クスクス。この年、当時大統領だったケネ
ディが暗殺され、その日からしばらく授業が中止になった事もあったそうです。
また、劇場が沢山あるリンカーン・センターというところで、水の上に舞台を設置、ヘンリー・ムーア
の彫刻のそばで『三番叟』『茸』を演じた事も。水の演出が効果的で大変美しかった、とも。
話はここ横浜能楽堂について。万作師曰く「横浜能楽堂が一番好き(笑)」。何故かと言えば、柱
が細いから(大笑)。もちろんその真意は「柱が細いと、確かに豪華ではないがあったか味がある
客席と近い感じがして良い」という事だそうです。よくよく柱を見たら・・・確かに細いかも(笑)。
海外公演に行って良かった、と思うのは「外国から帰って来て、万作は良くなった」と言ってくれた
人がいたから、との事。20代~30代はまだ父の元で基礎を習っている段階で、まだいわゆる「売
モノ」にはなっていない状態。日本では見所が「ああ、ここまで型が出来てきたな」といったような
修行の過程から見られている感じがするが、外国ではその役者が修業してきた過程やその成果
といったような見方はせず、その場でどれだけ面白いかに注目しているので、その点は大変新鮮
に感じたそうです。
インドや旧ソ連のレニングラードでの公演にも話が及びます。特にレニングラード公演では、舞台
が終わると観客が土足で舞台に上がり、プレゼントを渡そうとするのを関係者が必死に押し止め
るといった場面にも遭遇、ちょっと困りながらも(笑)、率直な反応が嬉しかったそうです。
レニングラードでは岡田嘉子さんに会われたそうですが、異国の地で聴く岡田さんの美しい日本
語に感動したとの事。「美しい日本語」という事で話は突如「にほんごであそぼ」へ(爆笑)。どうや
ら息子さん(笑)に続いて万作師も番組に登場予定だそうです!!それも「でんでんむしむし」で!
息子さんとオンナジ、恐竜タキシードをお召しになったらどうしましょ?!などと想像してしまった私
はホントにMAX阿呆(爆)。「若い者がやるのが良いと思ってましたが・・・」と、ちょっと照れていら
したようにも見えました(笑)。
最近の海外公演では演劇関係の人々も多く観に来てくれるそうで、とても嬉しいことだと仰ってい
ました。昔だったら「日本文化に興味があるから」といった理由で伝統芸能を観に来る海外の観
客が多かったそうですが、やはり「異文化だから」という理由よりも、「一演劇として興味深い」と思
って観ていただく・・・他の演劇と対等に感じていただくようでありたい、との事でした。
狂言は「素手の芸」であり、何も無いところからイマジネーションを湧かせて観る舞台であるので、
言葉の壁を越えやすいし、海外でもこの点で勝負出来るのが強い、とも。
海外でいろいろなジャンルの舞台を観るたびに「参加型の舞台は良いなぁ」と思われるそうです。
特に米国で観た歌手ハリー・ベラフォンテのステージ。"Let's sing together!"といった風に客席を
煽って一体感を引き出す。「倅がやっている『電光掲示』もそういったものですよねぇ」と、ちょっと
くすぐりも入りました(笑)。
もっと沢山話されていて、全て正確にここに記する事が出来ないのですが、万作師は終始大きな
身振り手振りでエネルギッシュに語って下さいました。海外公演の裏エピソード(爆)、まだまだあ
りそうな感じ(笑)。思い出を語られる時の楽しそうな笑顔が印象的でした。
13時の部と16時の部、2回『文蔵』の長い語りを終えられてからのトークでしたので、正直お声が
かなり辛そうな時もありましたが、見所も何度も何度も笑いましたし、時間があっという間に過ぎて
いった感じがしました♪
Ⅳ 狂言『弓矢太郎』 太郎:野村萬斎 当屋:石田幸雄 太郎冠者:竹山悠樹
立衆:深田博治・高野憲和・月崎晴夫・破石晋照
天神講(菅原道真の命日に行われる天満宮の祭)で当屋の家に集まった男達が、
臆病な性格の為いつも弓矢を携えている太郎の噂をしているうち、彼を脅かしてや
ろうと相談がまとまる。そこへ遅れて狩姿の太郎が登場、田畑を荒らす獣や狼藉者
を追っ払う為に日夜見張っているのだ、と威張る。狐でさえも射てみようという太郎
に、計画通り当屋が妖狐玉藻の前の故事を語る。瞬く間に恐ろしくなった太郎、そ
れでもどうせ古い話だろう、と気を取り直すが、今度は男達の一人が天神の森で鬼
に出くわしたという話を聞いて目を回して倒れてしまう。皆に起こされて「面白い話だ
ったので、ついうとうと寝入ってしまっただけだ」とうそぶく太郎、当屋に「夜の天神の
森に行って、松の木の一の枝に扇をかけて来れば鳥目(銭)百貫約束しよう」と持ち
かけられる。当屋は鬼に変装して天神の森に先回りして太郎を脅かす、と計画する
が、太郎は太郎で妻にハッパをかけられて、やはり鬼の変装をして天神の森へ。
真っ暗闇の中で変装した二人が鉢合わせ、二人とも気絶してしまう。先に気が付い
た太郎は森の中に身を隠すと、松明を手にした男達が様子を見にやってくる。倒れ
た当屋を起こして話を聞いていると、いままで木陰に隠れていた太郎が再び鬼に変
装して登場、、当屋と男達をしたたか驚かせて追い込んでいく。
オカルト・コメディー(全然違っ!)ですか??
まずいきなり笑ったのは、当屋が「幸雄殿」と呼ばれている事(笑)。
天神講で集まった男達、にぎにぎしく挨拶を交わすと話題は速攻、
臆病太郎の事へ。今日、太郎も一緒に集まる予定だったのだが、毎
日弓矢を携えてパトロール中(笑)。弓矢を携えていたところで、実際
弓矢など射たことも無いのが男達にバレバレ。どうやらこの太郎さん、
他人に驚かされないように弓矢で武装しているつもりらしい(苦笑)。
それならばますます臆病者を驚かしてみたくなるのが人間心理♪太
郎が遅れているのをいいことに、太郎を驚かす計画を立てます。立衆
が舞台向かって右側にキレイに整列して、当屋の計画を聞きながら、
「そりゃあ良い!はーっはっはっは!」と声を揃えるのが何とも可笑しい。みんな、腹の中は真っ
黒なんですが、なんとなくマヌケな感じ(笑)。
そこへ遅れてやって来ました萬斎太郎。弓矢を携えての狩姿は勇ましい(ホントに勇ましいか?)
んですが・・・橋掛かりを歩いてくるその歩き方が「山伏」とオンナジ(笑)。膝を高く上げていかにも
偉そうなんですが、実はへっぽこという。
太郎がやって来たのに気づいた当屋達、さっそく計画を実行に。家の中に招かれて「自分は田畑
を荒らす動物や狼藉者を追っ払う為に弓矢を持って見張っているのだ!」「さっきも大きなイノシシ
を一頭射抜いて退治したぞ!」と自慢(もちろんウソ)する太郎に、「ならば狐でも射抜けるか?」と
そそのかす。「もちろん!」と空威張りの太郎に、鳥羽天皇時代の妖狐・玉藻の前の故事を、実に
神妙な面持ちで語る当屋。石田当屋、なんとなく講談の怪談モノを語るような雰囲気(笑)。横で男
達はしらばっくれて聴いてます。石田さん、語り口がちょっと様式がかって怖いです♪
すると、さっきまで余裕の表情だった太郎、にわかに顔つきが硬くなる(笑)。話がはじまったとた
んにビビリ始めます!態度が落ち着かなくなり、袖の下の手がカタカタ震えてる(苦笑)。その豹変
ぶりが笑いを誘います。
なんとか我慢して最後まで話を聞いた太郎、気を取り直して大笑いし「でもソレはあくまで昔の話。
今の狐はそんな事をするはずがない!」と一蹴しようとします。しかしそこはどうしても太郎を驚か
せたい当屋、「いやいや、今の狐だって恐ろしい。狐は化けるというから、こうやって家の中で話を
している私達の中に、狐が化けている者がいるかも知れないぞ!!」とたたみかけます。またもや
ビビリ顔になる太郎に更に追い打ち。「今外を背にしている太郎さんの後ろで何かが光ったような
・・・」太郎、大パニック(爆)!!「ひえええええ!」とそこから逃げようとするも半分腰が抜けてる
(大笑)。「ば、場所代えてえええ!」と、今まで当屋が座っていた位置(舞台中央)に陣取ります。
彼の君・・・こういう役やると絶好調だなぁ(大笑)。
やっとの思いで持ちこたえた太郎に、今度は立衆の一人(深田さん)がまたもや怖い話を。夜、天
神の森で鬼に遭遇した、と言う。目が爛々と光っていたとか、口が耳まで裂けていたとか・・・さも
恐ろしげに鬼の様子を語ります。それを聴かされた臆病者太郎、今度は我慢出来ずに「あああ~
~~・・・」と妙な声を上げて、白目をむいて仰向けにひっくり返る(笑)!!あまりの恐怖に目を回
して気を失ってしまいます。舞台中央、両手を広げて白目をむく彼の君(爆)。可笑しいやら可愛い
(ヲイ)やら・・・。見所爆笑♪太郎はひっくり返ったままピクリともしません。
見事失神した太郎の周りで当屋達が笑う笑う!太郎の体をゆっくり起こして皆で「太郎さん、太郎
さんっ!」と起こしにかかります。ハッと気が付いた太郎、それでもまだ強がって言い訳をする。
「鬼の話があんまり面白かったんで、そのうち気持ちよくなってついウトウトしただけですっっ!」あ
の~・・・面白くって思わず眠っちゃう、ってアリなんでしょうか??
強がれば強がるほど墓穴を掘りまくる(苦笑)太郎に最後のワナ。夜、天神の森に行って来られ
れば鳥目百貫を出そう、と当屋が持ちかけます。そらもう、死ぬほど怖いのは当然ですが、鳥目
百貫と言われたら引き下がるワケにはいかない。その証拠として、森の松の木の一の枝に扇を
かけてこい、と言われ「やったろーじゃねーかー!!」とばかりに、勇んで支度に出て行く太郎。
後に残った当屋達、またもや笑い転げます。当屋が鬼に変装して、先回りして天神の森で太郎を
待ち伏せ、したたかに驚かせてやろうという目論見。男達は後から赴いて、また白目をむいて気
絶しているであろう太郎をからかってやろう、とほくそえんでいます。いやもう皆さん人が悪いんだ
から(苦笑)。
さて夜も更けた天神の森。まず現れたのは当屋が変装した鬼。「蓬莱の島からやってきた鬼だぞ
ー!」と言っていますがもちろん当屋。ここでも「山伏ウォーク」風(笑)での登場です。
約束の場所まで来てみましたが・・・さすがに夜の天神の森、肝試しをしかけた当屋当人にとって
もかなり怖い(笑)。しかけておきながらビビッてる当屋・・・情けないです。
そのうち、今度はいよいよ太郎がやってきます。見ればなんと太郎も、当屋と寸分違わぬ鬼のい
でたち!「女房に、鳥目百貫しっかり取ってこい!ときつく言われてしまった・・・」とぼやきながら歩
いています。鬼が出る、というのならこっちも鬼の格好をしてしまえ、という発想でしょうか(笑)?
こちらも夜の天神の森の不気味さにビビリまくっております・・・。
真っ暗闇で何も見えない中、お互いの気配や物音に気づいた二人、手探り&へっぴり腰でそこら
中を探し回ります。お互い、相手に触りそうで触らない(笑)。うろうろと歩き回るうちについに接触
!鬼の格好のままピキーンと固まる二人(大笑)。ここからのアクションが、またもや「萬斎&石田
ゴールデン・コンビ」の見せ所♪♪背中や頭をくっつけたまま、おどおどしながら回ってみせます。
へっぴり腰状態がとにかくコミカル。ついには至近距離で顔を合わせてしまい、「ぎゃーーーー!」
と叫びながら二人とも舞台中央で仲良く並んで気絶(爆)。特に当屋、何の為にここに来たんだか
(苦笑)・・・。
先に気づいた太郎、もうここにはおれん!と森を出て行こうとしますが、ちょうどおり悪く男達が様
子を見に松明をかかげてこちらにやって来るではありませんか!惨めな姿を晒すわけにもいかず
慌てて木陰に身を隠します(後見のところで背中を向けています)。
男達は松明をゆっくりと回しながら登場。この松明の小道具が・・・炎に模したモノはいったい何だ
ったんでしょう?遠くから見ると「赤い羽根」みたいで可愛いというかショボいというか(苦笑)。
地べたにひっくり返っている「鬼」を発見、すぐに当屋だと分かって起こしにかかります。気が付い
た当屋、自分が鬼に遭遇してしまった!と震えながら説明します。「そんなバカな」という表情で話
を聴いている男達の後ろで、太郎は密かにスススーと橋掛かりへ。当屋が「目は明星のように爛
々と光り、真っ赤な口が耳まで裂けていて、腕は毛むくじゃらで・・・・」と、事細かに鬼の様子を語
るのですが、その語りに合わせて、橋掛かり上の太郎がいろいろと愉快なポーズを♪
「目が爛々・・・」と聞けば両手の指で丸を作って両目に当て、「口が耳まで・・・」と聞けば口の端か
ら耳のところまで指でなぞって"裂けている"仕草をしたり、「毛むくじゃらの腕が・・・」と聞けば袖を
大きくまくって腕を見せてアピール(笑)。見所、橋掛かりに釘付け(大笑)。太郎さん、遂に自分が
騙されていた事に気づきます。
「もしかしてこれは事実か?」と怖がりだした当屋達の背後に、鬼の面を着け直した太郎がソーッ
と忍び寄る・・・当屋の後ろから「うおおおおおっ!!」と叫ぶ太郎!泡喰った当屋達、ほうほうの
ていで逃げ出します。それを情け容赦無く(笑)追い込む太郎@鬼。
最後まで賑やかな演目でした。和泉流のみが所演するそうです。
解説とトークが一つずつ、演目が二つと、なかなか盛りだくさんな内容でした。『文蔵』では万作師
の勇壮な戦語りを十二分に堪能出来たし(これ、ホント聞き入ってしまいました)、『弓矢太郎』で
はへっぽこ太郎の情けない姿に大笑いさせられました。海外公演の思い出話を語る万作師の本
当に楽しそうなキラキラした表情が忘れられません。今年はまた海外公演があるそうなので、新し
いこぼれ話に期待です(笑)。

(橋掛かり方面)