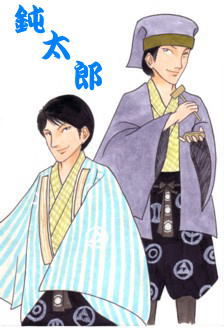2002年10月24日(木) 18:30〜 於:宝生能楽堂
【番組表】
『伊文字』
女・使いの者:野村万作 主:高野和憲
太郎冠者:野村万之介 後見:月崎晴夫
『縄綯』
太郎冠者:野村萬斎 主:野村万之介
何某:石田幸雄 後見:野村良乍
『鈍太郎』
鈍太郎:野村萬斎 下京の妻:深田博治
上京の女:高野和憲 後見:竹山悠樹
国立能楽堂のがハズれまして(苦笑)、期せずして二度目の宝生能楽堂となりました「狂言ござる乃座
28th」。「青き月の小部屋」管理人の波華様と初対面致しまして気分も上々!「小舞の会(7月)」の際
萬斎氏&サヤちゃんが出没(笑)したという金毘羅様を横目で見ながら二人で会場へ。
玄関から入ってすぐ目に飛び込んだのは、「陰陽師」原作者・夢枕獏先生からのお花!おお〜!宮島
での「パート2クランク・イン決定」発言を受けて(?)の贈り物でしょうか?周りからも「あ、夢枕先生の
・・・」という声がアチコチから。うむむ、既に発表された事ですが、ここであらためて実感・・・。
受付を済ませ(この時萬斎ワイフは受付にいらっしゃったんでしょうか?確認出来ず)能楽堂の中へ。
う〜ん、やっぱり良いですねぇこの雰囲気。「小舞」以来ハマッています(笑)。今回の座席は抽選によ
り中正面席6列目。今宵の敵は「目付柱」(爆)。席番はやや正面席よりだったのが幸いして、なんとか
「目付柱が視線のど真ん中」という事態は免れたようです。
★★★★★
『伊文字』
〔あらすじ〕 妻乞いの祈誓の為に清水観音に詣でた主人は、そこで「西門の一の階(きざはし)に立つ
女を妻にせよ」という霊夢を見ます。夢のお告げの通りにその場所に行ってみると、案の
状女が一人立っていました。「恋しくば問うても来ませ伊勢の国伊勢寺本に住むぞわらは
は」と歌を詠んで女は忽然と姿を消してしまいますが、女の後を追いたい主人と太郎冠者
は、忘れてしまった女の歌の上の句「・・・来ませ、い」以降をなんとか思い出そうと、関を
作って道行く人々を留めては訊ねます。使いを急ぐ男を無理矢理引き止めて訊ねると、
その男、「『い』の字の付く国の名前」であると推測して、試行錯誤ののち「伊勢の国」であ
ると思いつきます。太郎冠者が「なるほど!」と喜んだのも束の間、今度は「・・・伊勢の国
・・・い?」でまたもや詰まってしまい・・・。
高野さんの「主」に万之介師の「太郎冠者」。高野さん、観る度にかっこよく凛々しくなっていく感じがし
ます。この方の声、非常に通りが良くて気持ちが良い!万之介師の「太郎冠者」というのは、生の舞台
でも映像媒体でも自分にとっては初めてで、どのようなものかなぁ、と思っていたのですが・・・とぼけた
味にホンワカとした気分になってしまいました。いたずらっ子のような萬斎氏の太郎冠者(映像媒体の
みですが)の印象が非常に強かったのですが、演者が変わる事によって「太郎冠者」の印象もこれほ
ど変わる。こういう見比べがこれからの楽しみの一つになるかと。
万作師の女姿もこれまた初見(笑)。顔は完全に隠れていて表情は分かりませんでしたが、「恋しくば
・・・」の歌を詠む声の艶っぽい事!すすすっと橋掛かりを歩いてくる姿も優雅です。「嗚呼、一度でいい
からご尊顔を拝見したい!」と思ってしまいました(苦笑)。歌だけ残して幻のように去ってしまう女。顔
が見えない分ミステリアスな感じです。さて主と太郎冠者、どうしても歌が思い出せない!高野さんと万
之介師が「・・・来ませ、いーっ?」と詰まってしまう度に見所が笑いに包まれます。・・・それにしても、歌
を思い出す為に、長襷で関所を作って道行く人を捕まえては訊き出そうとする・・・ナンセンスですよね
ぇ(笑)。このナンセンスさが、能舞台の上では全く違和感無し。そこに急ぎの使いの万作師登場!先
ほどのミステリアスな女の雰囲気とは打って変わって、力強い台詞回しに聴き入ってしまいます。
「伊の字のつく国の名は〜♪」と謡いながら、万作師は被っていた笠を舞扇に見立てて(?)大きく円を
描くように優雅に舞います。何か答を思いついたのか、舞いながらニンマリとする万作師・・・この「ニン
マリ顔」が、一瞬萬斎氏にソックリでした(親子なんだから当たり前なんですが・汗)!ここまで3回ほど
万作師を拝見したのですが、今回のこの瞬間ほど「ソックリだ!」と思ったことはありません。「伊勢の
国」が出るまで歌は繰り返されますが、子供の遊び歌・・・たとえば(パンフにも書かれていましたが)
「花いちもんめ」のような、なんとなく懐かしい牧歌的な感じが見所を支配します。ちょっと一緒に歌いた
くなるような暖かい楽しさ。自分が歌っちゃいそうであぶなかった(苦笑)。
最後には女の残した歌の全貌を思い出して、主・太郎冠者・使いの者三人で名残の謡を朗々と謡いな
がら退場して行きます。何故か橋掛かりの向こうに夕焼けが見えるような(笑)。ここでちょっと残念な
事が。幕に入る前にパラパラッと拍手が起こっちゃったんですが・・・一度止まって戸惑ったような雰囲
気になり、またパラパラ、また止まり・・・と、統一性のない拍手になっちゃったんです。凄く間が悪い。こ
このところ、橋掛かりの拍手の件についていろいろ意見が出ていたところだったので、拍手すべきでな
いのか、しても良いのか、と見所が戸惑ってしまったのでしょうか?せっかく良い雰囲気の大団円だっ
たので、バラバラな拍手が残念でした。あと、演者が完全に幕に入る前に席を立つ人がチラホラ・・・何
の目的かは分かるんですが(苦笑)、やっぱりねぇ・・・。 始まる前の見所の雰囲気が良かっただけに
残念です。生理現象には勝てなかったか・・・。
★★★★★
『縄綯』
〔あらすじ〕 博打に弱い博打好きの主人、何某との勝負でまたもや負けてしまい、賭けの対象にしてし
てしまった太郎冠者を取られてしまう事態に。太郎冠者に本当の事を言えない主人は、
書状を届けるという名目で何某の家に太郎冠者を送ります。そこで自分が賭けの対象に
されていた事を知った太郎冠者、すねてしまい何某の言う事を全く聞きません。頭に来た
何某、役立たずの太郎冠者など金銭に変えてしまえ、と怒りますが、主人は一度太郎冠
者を自宅へ戻して、本来の働き者ぶりを見て欲しい、と何某に頼みます。そうとは知らぬ
太郎冠者、主人の元に帰れてホッとしたのか、得意の縄綯いをしながら何某の家族に対
する罵詈雑言を面白おかしく並べ立てます。面相の醜い何某の妻の事やら、行儀の悪い
子供達の事やら・・・散々言い立てているところに当の何某が現れて・・・。
いよいよ萬斎氏の太郎冠者です!それも(悪口雑言とは言え・笑)長台詞付き!主人の名は「万之介
殿」、何某の名は「幸雄殿」と、演者の本名をそのまま使っているのが何ともオカシイ。萬斎太郎冠者、
実は自分が借金のかたにされているという事を知って愕然、完全にヘソを曲げてしまいます。幸雄殿
に声をかけられても後ろを向いたまま。更に声をかけられると、お尻をモゾッと浮かせて「プイッ」と更に
顔を背けてしまいます。この「プイッ」がもう可愛くて(大笑)。山向こうへ使いに行けと言われれば「持
病の脚気で出来まっしぇーん!」、縄を綯えと言えば「そんな賤しい仕事なんかやった事ありまっしぇー
ん!」と徹底的に反抗(笑)。もうその不貞腐れぶりに笑わされます。一旦主人の元へ戻った太郎冠者
ですが、さっきの反抗的な態度が一変。従順な態度を見せながら「ご主人様は博打の才が無いのだ
から、もう止めましょうよ」と気遣ったりする、忠義の家来です。
さてココからが「発散型狂言師(笑)」萬斎氏の独壇場!主人の元に戻ってホッとしたのか、主人に頼
まれた(実は主人がコッソリ何某に太郎冠者の真の働きぶりを見てもらおうと画策)縄綯いをしながら
何某の家族の悪口をまくし立てます(そんなにイヤだったのか何某の家・・・)。まずは何某の妻の容姿
に罵詈雑言!「髪の毛が薄い」だの「鼻よりほっぺたが前に出てる」だの「お尻が平たくて大きい(・・・
どんな尻じゃそりゃ)」だの・・・それを一人で長台詞の中で表現する萬斎氏の声や表情のヴァリエーシ
ョンが本当に豊かなんです。まるでお正月の福笑いのように、何某の妻の顔のパーツを頭の中で組み
立ててしまう私(苦笑)。舞台では「幸雄殿の・・・」と言っているので、更にオカシイ。そうやってあーだ
こーだ言っているのと同時に縄を綯っているんですが・・・それなりの手つきの割りには綯えていない
んですねコレが(笑)。多分あくまで舞台の上では綯う「真似事」ですから、キチンと綯う必要は無いん
でしょうが・・・ここでちゃんと綯えていたら、萬斎氏のかっこよさ三倍増だったのに。ま、いっか(笑)。
借金のかたにされたり、「賤しい」と言われる縄綯いの仕事をしたり・・・太郎冠者というキャラクターは、
どうもあまり人権を認められていない存在のようですね。帰宅してから調べたんですが(もうほとんどの
方達には周知の事実でしょうが・汗)やはり下人階級・隷属民だったそうです。この演目では、そういう
太郎冠者のちょっと哀しい立場や、騙されても主人を慕う忠義ぶりがハッキリと伺えます。むしろ、その
ような立場を嘆く事無く、ユーモアとヴァイタリティーで笑い飛ばしてしまう「強さ、したたかさ」みたいな
ものも感じられます。萬斎氏の「太郎冠者」は、今までではスマートなイメージが強かったのですが、こ
の演目では、両の腕にグイッと力を込めて縄を綯う姿(・・・綯えてないんですけどね・笑)がいつもと少
し違う印象を持たせてくれました。骨太な太郎冠者に見えました。こちらもなかなか良いです(笑)。
やがて悪口は何某の子供達にも飛び火。膝に乗せたら髪の毛を引っ張られたり耳の穴に指を突っ込
まれたり散々だった、あまりに悪戯が過ぎるので裏庭に連れて行って一発お見舞いしたら・・・そこに
例の奥方が「夜叉」みたいな顔をして立っていた・・・萬斎氏の表現力でその様子がどんどん浮かんで
きます!悪口雑言が最高潮に達したところで、太郎冠者の背後に異変が。今の今まで後ろにいたと思
っていた主人が、いつの間にか何某幸雄殿にすりかわっている!何も知らずに調子に乗りまくる太郎
冠者、ふと後ろを振り向くと・・・ガーーーーーンッ!!ゆ・き・お・ど・の!太郎冠者萬斎、「鳩が豆鉄砲」
の表情で全身硬直(爆)。出ました!セルリアンに続き「石化萬斎(笑)」。今度の方が石化時間が長い
です。無言で太郎冠者をジーッと睨む何某幸雄殿、怖いです(苦笑)。そろーり、そろーりと逃げ出そうと
する太郎冠者に何某一喝!「ご許されませ、ご許されませぇぇ〜っ!」と追い込まれる太郎冠者萬斎の
マジで大焦りの表情に会場大爆笑!太郎冠者は冷や汗タラーリ、こちらは笑い過ぎて大汗かいちゃい
ました。
★★★★★
『鈍太郎』
〔あらすじ〕 3年間、何の音沙汰も無く西国に滞在していた鈍太郎が京の都に帰って来ました。まず下
京の妻のところへ赴きますが、まさか夫が帰って来たとは思わない妻は「棒遣いの男と再
婚しました!」と言って追い返してしまいます。仕方なく鈍太郎は上京お妾さんの許を訪ね
ますが、こちらでも信じてもらえず「長刀遣いの男と一緒になりました!」と、同じく追い返
えされる始末。二人に振られて落胆しきった鈍太郎は出家を決意してしまいます。後にな
って勘違いだった事を知った二人の女がうろたえていると、そこに出家姿の鈍太郎が登
場。詫びる女達に鈍太郎はある提案を。「上半月は上京の女の家、下半月は下京の妻の
家で過ごす・・・」虫の良い約束を取り付けた鈍太郎は挙句の果てに・・・。
二股かけてる調子の良いモテ男クンのお話(笑)。遊びが過ぎて正妻・お妾さん両方からあいそをつか
されてしまします(自業自得)。二人とも別の男に取られてしまったと思い込み「南無三!」と体を曲げて
手を叩き悔しがる鈍太郎萬斎・・・その悔しがる姿がこれまたお父上万作師にソックリなんです。さっき
の「伊文字」では万作師のニンマリ顔が息子さんにソックリで・・・親子だから当たり前なんですが、ふと
した瞬間、見た目から雰囲気から、本当に良く似ていらっしゃいます。
振られたショックで出家してしまう、というのもなかなか唐突なんですが(苦笑)、勘違いで起こったこの
事態にうろたえて、本来なら反目し合うはずの正妻と妾が落ち合っている。現代なら流血付きの修羅場
でしょうに、なんとものどかな雰囲気です(笑)。そこに出家姿の鈍太郎登場!「南無阿弥陀仏〜♪」と
鉦鼓を叩いて唱えながらこちらへ向かってきます。 その読経の声が朗々としてまた良いのですが、坊
主になってもあまり(と言うか全然)解脱したように見えないところが可笑しい。必死に出家を思いとどま
らせようとする二人の女に挟まれて、鈍太郎クンまんざらでもない様子(笑)。
やや大柄でしっかり者そうな正妻・深田さん、小柄で可愛らしいお妾・高野さん。二人の女の対比が効
果的です。鈍太郎は正妻よりも、この小柄でちょいコケティッシュなお妾さんの方がお気に入りのようで
それはもう目に余るほどの「えこひいき」ぶり!二つの家を行き来する事で二股状態を保とうとするの
ですが、いきなり「一ヶ月の間、25日間はお妾さんのところ、あとの5日間は正妻のところ」などという
メチャクチャな条件をつけようとします。そんなにイヤか深田正妻(苦笑)。「それは出来ない」と言われ
れば、「じゃあやっぱり出家しちゃうよ〜」と念仏唱えてその場を去ろうとする。慌てて止めようとする女
二人。悪いやっちゃ鈍太郎。でもなにか憎めない「調子の良い男」なんですねぇ。
さすがに不公平な条件なので、「それでは上半月を上京で、下半月を下京の妻のところで過ごす」と約
束するのですが・・・一見平等そうなこの条件、情けない「裏」が!当時は太陰暦だったので、小の月は
29日間。なんと上半月は下半月より一日多くなる計算なのです。たった一日多くお妾さんのところで過
ごしたいが為のトリック(笑)なのでしょうか・・・セコい!セコ過ぎるぞ鈍太郎〜っ!嗚呼、でもこの二人
女、惚れた弱みなのか条件を飲んでしまうのね。懐が深いわ当時の女性(感嘆)。そんな話でも、何故
か「これは女性に対する差別だ〜!」などとは思えません。都合よく物事を運ぼうと思っている小ずるい
(でもなんかカワイイ)男と、それを「やれやれ」と思いつつ認めてしまう大らかな女性達。修羅場の影も
ございません。鈍太郎萬斎の「してやったり」顔が笑いを誘います。
鈍太郎が「手車」をしてくれと言うので、二人の女は互いの両手を騎馬戦の馬のように組んで用意しま
す。それに鈍太郎が乗り込むまでの間に、やはり「伊文字」にもあったような子供の遊び歌のようなか
けあいが三人の間で始まります。
「これは誰が手車〜♪」 「鈍太郎殿の手車〜♪」
コレを何度も何度も繰り返すのですが、その間にも鈍太郎は鉦鼓を鳴らしながら踊ります。正妻とお妾
さんの間をクルクルと回りながら歌うのですが、お妾さんには鼻の下を伸ばした顔を向け、時には「いい
こいいこ」までするのに対し、正妻にはしかめっ面で「しっしっ!あっち行け!」と言わんばかりの態度。
「そこまでやるか」とも思いますが、三人のかけあい歌の素朴さに助けられたかイヤな感じはしません。
ただ「いくら出家を思いとどまらせようとする為とはいえ、なんでこんなに正妻とお妾さんが仲良いの?」
という疑問はあります(笑)。そこを修羅場にしないところが「狂言」のなせる業か?
女二人の手車に乗った鈍太郎、担がれたまま橋掛かりへと退場しますが、深田さんと高野さんの身長
差があるので、萬斎氏の体がちょっと傾いでいてドキドキ(苦笑)。それでも二人の女を手玉に取って
意気揚々の鈍太郎は満面の笑み!担がれていくさまの滑稽さとかけあい歌の愉快さに、橋掛かりの途
中から見所はやんややんやの大喝采となりました。パンフの萬斎氏の挨拶文にもありましたが、「女か
ら見れば『男の理想』に過ぎないのですが・・・」確かに。シツコイようですが、現代なら修羅場です(笑)。
でもわざわざ挨拶文で言い訳されなくとも、能舞台の上では「お調子者の可愛い男」だったのでは?